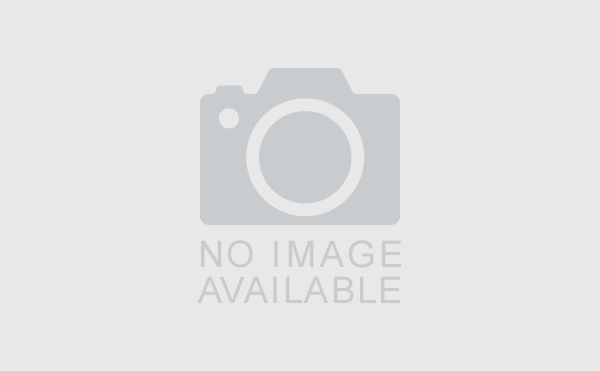瀧水会長と稲作り
我が蒔ける早稲田の穂立作りたる かづらぞ見つつ 偲はせ我が背(万葉集)
8月26日、「向陽みどりのボランティア」の西崎さんから、「初めて稲を育ててみた」とのご連絡をいただきました。クラブハウスの裏手、テニスコート隣の畑へ見に行くと、発泡スチロールの「田んぼ」の中に、黄金色になりつつある稲穂が。
西崎さんにお話を伺いました。
「5月に、柏の宮公園の水田で栽培する苗が余ったから、と『柏の宮公園自然の会』さんから代表の新木さんにお声がけがあり、苗と荒木田土(注1)を譲り受けました。発泡スチロールの箱をスーパーからもらってきて、3箱に荒木田土を、もう3箱には陶芸サークルから分けてもらった粘土に畑の土を混ぜて、苗床を作りました。
みどりのボランティア歴10年の私も稲作はまったく未経験なので、メンバーたちと共に、日当たりや水の管理、肥料やり、草取りなど、何もかも手探りでした。米農家さんのご苦労がよくわかりました。」
「向陽みどりのボランティア」は、向陽中ボランティア部の生徒さんたちと一緒に活動しています。「都会の中学生に、稲がどんなふうに成長してお米になるのか、知ってもらえる一助になれば」と西崎さん。


ところで、柏の宮公園の水田で稲を育てている『柏の宮公園自然の会』は、先月ご逝去された瀧水会長が発足時から関わり、尽力されてきた団体です。会の代表で苗のおすそ分けをお声がけくださった宮内隆夫さんは、瀧水会長とは高井戸第三小・向陽中での同級生。
宮内さんは会長のお通夜に、リボンをかけた稲穂を手に参列され、「今年の稲穂です」とお供えしてくださいました。告別式の後、稲穂はご遺族の手でお柩の中に。
冒頭の万葉集の歌(注2)は、「私が蒔いて実った早稲(わせ)の田の稲穂で作ったかづら(髪飾り)を見て、私のことを思い出してくださいね」との意味。
西崎さんから稲作りのご連絡をいただいたのは、会長が亡くなられた翌日のことでした。「きっと稲穂になって、会長が向陽中に帰ってきたんですね」と西崎さんも巡り合わせに驚かれていました。
向陽中の畑で稲穂を見ると、会長の笑顔が思い出されます。
注1:水田の底から採取される粘土質の土。非常に保水性が高く、養分の保持力にも優れている。
注2:奈良時代の歌人、大伴家持の正妻となる坂上大嬢が家持に贈った歌。